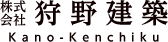土地探しのポイント
注文住宅を建てるのに一番重要なのは住む場所の土地や環境です。中古物件を購入して何年かしてから家を建て替える方や土地を購入して注文住宅を建てる方、また、建売を購入する方様々だと思いますが、長く住むぬですから廻りの環境はすごく大事です。その中で土地購入するポイントがあります。
「廻りの環境」土地を購入するのにまず何を重視するかを考えると良いと思います。例えば、車をお持ちで駅などが多少遠くても静かな場所がいいとか、車を持っていないので駅に近く、近所にスーパーやコンビニなどがある場所に住みたい。また、子供がいるので学校に近い方がいいなど様々あると思います。このような些細なことから土地選びは考えてみても良いと思います。
「注文住宅を建てるのが可能な土地か」何年か住んでから注文住宅に建て替えるため中古物件を購入する場合、注意しなくてはならないのが、(再建築不可物件)の土地には気を付けた方がいいです。(再建築不可物件)になる土地で一番多いのは、(接道義務)を満たしていない土地が多いです。あまり聞きなれない言葉だと思いますが、簡単にいえば緊急車両(救急車や消防車が通れる経路の確保が出来ていないといけません。その為、建築基準法では幅4メートルの道路に土地が2メートル以上接した土地でなくてはいけませんまた一部の区域では6メートル以上の幅を必要とされる場所もあります。また、旗竿地なども2メートル未満の場合は再建不可になりますので気を付けた方がいいです。ただ例外もありまして、建築基準法が施行された日の昭和25年11月23日またはその土地が都市計画区域になった時点に建物が建っていた場合、道路中心から2メートルとれるよう(セットバック)して建てることができます。道路挟んで川や崖などの場合は道路境界線から4メートル(セットバック)して再建可能です。このことを(2項道路)と言います。ただしセットバックした場所にはフェンスや門扉なども建てられず、土地として使用出来る面積は減ります。「その土地に対してどれくらいの大きさの建物が建てられるか?」どの土地にも必ずしも希望通りの住宅が建てられるわけではありません。土地には建ぺい率と容積率といった都市計画法や建築基準法でその地域ごとに建物の高さや大きさが制限されています。(建ぺい率)建ぺい率とは敷地の面積に対しての建物の面積の割合のことを言います。簡単に説明すると、上空から建物を見たときの建物全体の面積のことです。(容積率)容積率とは、敷地の面積に対しての延べ床面積の割合のことです。建物のすべての床面積のことを延べ床面積と言います。建ぺい率・容積率共用途地域により異なるので、市区町村の都市計画課で確認することができます。また、建ぺい率が緩和される場合もあります。「街区の角にある敷地」「道路に挟まれた敷地」「公園・広場・河川などに接する敷地」は建ぺい率の上限が10%加算で緩和される場合もありますが、特定行政庁ごとに街区の角地に指定されている条件に適合している場合に限る為、必ず緩和されるものでもありません。また都心などには「風致地区条例」という都心に残された水や緑などの自然環境を守る地域に指定されている地区もあります。その場合も建ぺい率や建築物の高さも変わりますので注意が必要です。最後にこのような土地は購入しない方がいいです。「斜面に盛土をした造成地」斜面に盛土をして造成をした土地は崩落や地盤沈下などのリスクが高いです。現在の注文住宅を含む新築住宅は地盤調査をして地盤の悪い所は杭を打ちますので、昔に比べて建物が地盤の影響で傾くことは減りましたが、盛土は地盤沈下をするリスクが高いのでやめた方がいいです。「境界が確定されていない土地」中には境界が確定していない土地も売り出されていることがあります。本来ならば土地を購入する方に対して売主は隣接する土地との境界を明示する義務があります。(境界明示義務と言います)しかし、売主様の方で近隣と揉めてたり、中には意地の悪い人もいますので、土地を購入した後に揉める可能性もあります。境界の杭が見当たらなくとも境界を出すことも可能ですが、一生住むかもしれない土地なので近隣とのトラブルは避けたいですよね。「自然災害の受けやすい土地」自然災害とは暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波・噴火等中には思いもよらない災害があります。それをすべて回避して土地を探すのは不可能です。しかしなるべく被害の受けにくい土地を購入した方が安心です。自然災害を受けやすい土地は崖がある地域や傾斜地または、周囲よりも低い位置にある土地が多いです。軟弱地盤や高低差のある土地なども避けた方がいいです。高低差のある土地の土地価格はやすい傾向がありますが、建築するのに費用が高くなる傾向があります。まず高低差がある場合、建築費用に加えて「造成工事や擁壁」などの工事をする場合もあります。状況により深基礎で対応出来る場合もありますが、基礎工事には通常の基礎工事に比べ費用はかかります。また、道路との高さもあるので、建物に入るのに階段を上がらなければ入れませんので将来的には不便になる傾向があります。
「廻りの環境」土地を購入するのにまず何を重視するかを考えると良いと思います。例えば、車をお持ちで駅などが多少遠くても静かな場所がいいとか、車を持っていないので駅に近く、近所にスーパーやコンビニなどがある場所に住みたい。また、子供がいるので学校に近い方がいいなど様々あると思います。このような些細なことから土地選びは考えてみても良いと思います。
「注文住宅を建てるのが可能な土地か」何年か住んでから注文住宅に建て替えるため中古物件を購入する場合、注意しなくてはならないのが、(再建築不可物件)の土地には気を付けた方がいいです。(再建築不可物件)になる土地で一番多いのは、(接道義務)を満たしていない土地が多いです。あまり聞きなれない言葉だと思いますが、簡単にいえば緊急車両(救急車や消防車が通れる経路の確保が出来ていないといけません。その為、建築基準法では幅4メートルの道路に土地が2メートル以上接した土地でなくてはいけませんまた一部の区域では6メートル以上の幅を必要とされる場所もあります。また、旗竿地なども2メートル未満の場合は再建不可になりますので気を付けた方がいいです。ただ例外もありまして、建築基準法が施行された日の昭和25年11月23日またはその土地が都市計画区域になった時点に建物が建っていた場合、道路中心から2メートルとれるよう(セットバック)して建てることができます。道路挟んで川や崖などの場合は道路境界線から4メートル(セットバック)して再建可能です。このことを(2項道路)と言います。ただしセットバックした場所にはフェンスや門扉なども建てられず、土地として使用出来る面積は減ります。「その土地に対してどれくらいの大きさの建物が建てられるか?」どの土地にも必ずしも希望通りの住宅が建てられるわけではありません。土地には建ぺい率と容積率といった都市計画法や建築基準法でその地域ごとに建物の高さや大きさが制限されています。(建ぺい率)建ぺい率とは敷地の面積に対しての建物の面積の割合のことを言います。簡単に説明すると、上空から建物を見たときの建物全体の面積のことです。(容積率)容積率とは、敷地の面積に対しての延べ床面積の割合のことです。建物のすべての床面積のことを延べ床面積と言います。建ぺい率・容積率共用途地域により異なるので、市区町村の都市計画課で確認することができます。また、建ぺい率が緩和される場合もあります。「街区の角にある敷地」「道路に挟まれた敷地」「公園・広場・河川などに接する敷地」は建ぺい率の上限が10%加算で緩和される場合もありますが、特定行政庁ごとに街区の角地に指定されている条件に適合している場合に限る為、必ず緩和されるものでもありません。また都心などには「風致地区条例」という都心に残された水や緑などの自然環境を守る地域に指定されている地区もあります。その場合も建ぺい率や建築物の高さも変わりますので注意が必要です。最後にこのような土地は購入しない方がいいです。「斜面に盛土をした造成地」斜面に盛土をして造成をした土地は崩落や地盤沈下などのリスクが高いです。現在の注文住宅を含む新築住宅は地盤調査をして地盤の悪い所は杭を打ちますので、昔に比べて建物が地盤の影響で傾くことは減りましたが、盛土は地盤沈下をするリスクが高いのでやめた方がいいです。「境界が確定されていない土地」中には境界が確定していない土地も売り出されていることがあります。本来ならば土地を購入する方に対して売主は隣接する土地との境界を明示する義務があります。(境界明示義務と言います)しかし、売主様の方で近隣と揉めてたり、中には意地の悪い人もいますので、土地を購入した後に揉める可能性もあります。境界の杭が見当たらなくとも境界を出すことも可能ですが、一生住むかもしれない土地なので近隣とのトラブルは避けたいですよね。「自然災害の受けやすい土地」自然災害とは暴風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波・噴火等中には思いもよらない災害があります。それをすべて回避して土地を探すのは不可能です。しかしなるべく被害の受けにくい土地を購入した方が安心です。自然災害を受けやすい土地は崖がある地域や傾斜地または、周囲よりも低い位置にある土地が多いです。軟弱地盤や高低差のある土地なども避けた方がいいです。高低差のある土地の土地価格はやすい傾向がありますが、建築するのに費用が高くなる傾向があります。まず高低差がある場合、建築費用に加えて「造成工事や擁壁」などの工事をする場合もあります。状況により深基礎で対応出来る場合もありますが、基礎工事には通常の基礎工事に比べ費用はかかります。また、道路との高さもあるので、建物に入るのに階段を上がらなければ入れませんので将来的には不便になる傾向があります。